退職者による情報漏洩はなぜ起きる?よくある“あるある”パターン

こんにちは、ixmedia編集部です!
最近、退職や人の異動が増えてきたなと感じること、ありませんか?
「最近、退職する人が多いなぁ」
「引き継ぎの準備、大丈夫かな?」
「…っていうか、あの資料、まだ残ってたりしないよね?」
そんな“小ささ”が気になる瞬間、ありませんか?
今の時代、転職やキャリアチェンジは日常。
でもその陰で、「人が辞めた瞬間に、情報がどこかに漏れていた」…なんてリアルな話も少なくありません。
今回は、そんな情報漏洩のリスクについて、
情報漏洩する典型的なパターンと、その中でも一番多い原因について、お話ししていきたいと思います。
情報漏洩の「原因と対策」をざっくり知っておこう
会社経営において情報漏洩を起こしてしまうと、
信用問題だけではなく、賠償問題などにも発展してしまう大きなリスクがあります。
情報漏洩についての原因と対策を知っておくことはリスク管理において重要です。
まずは、情報漏洩リスクの基本3分類について、ご紹介します。
情報漏洩の主な原因はこの3つ
1. 外部からの攻撃
ハッキング、不正アクセス、マルウェア、フィッシング詐欺など、外部の第三者が意図的に侵入・奪取するケース。
→ セキュリティ対策ソフトやアクセス制御、ファイアウォールなどの防御策が効果的です。
2.人為的なミス(ヒューマンエラー)
メールの誤送信、共有設定のミス、誤操作、不要ファイルの放置など、「うっかり」によって発生する情報漏洩。
→ 多くの場合、“本人に悪気はない”ことが特徴。再発防止には、教育や運用ルールの明確化が必要です。
3. 社内・内部からの不正または過失
退職者や現職社員が、意図的に・あるいは無自覚に情報を持ち出してしまうケース。
→ USBや私用クラウドへの保存、私物PCへの同期、チャットのログ残留など、“気づかないまま”起きるのが特徴です。
この主な原因3つとそれぞれの対策については、
以下の記事で詳しく解説しているので、まだ読まれていない方はぜひこちらも併せてご覧ください。
情報漏洩は、どんな企業でも無関係とは言い切れないリスクです。
社員一人ひとりの意識はもちろん、会社全体で仕組みとして守る体制づくりが欠かせません。
中でも見落とされがちなのが、“退職時”に生まれる情報のすきま──次はそこを見ていきましょう。
退職=情報が外へ流れやすい瞬間
実は「退職者」こそ、情報漏洩の一番多い原因って知ってましたか?
ここからは、情報漏洩の3大原因のうち、特に見落とされがちでリスクが高い「内部からの漏洩」、
その中でもとくに多い「退職者による情報漏洩リスク」にフォーカスしていきます。
「退職のタイミング=情報が動きやすい瞬間」──
これは、ただの比喩ではなく、実際に数字としても表れています。
IPA(情報処理推進機構)の調査データが示す“現実”
IPAによる「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」では、
情報漏洩について、以下のような実態が明らかとなっています。
-
営業秘密の漏洩ルートとして最も多かったのが「中途退職者」:36.3%
-
社内で起こる「現職社員の誤操作(21.2%)」よりも、明確に多い
-
一部の企業では「退職者経由の漏洩は防ぎようがない」と諦める声も存在
-
サイバー攻撃よりも、「人の異動」が最大のリスクになることも珍しくない
※出典:IPA「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」
なぜ「退職の瞬間」が危ないのか?
なぜ「退職の瞬間」が危ないのか?
退職そのものは、今や当たり前のキャリアの流れ。
ですが、“人が組織を離れる”というのは、同時に**「情報が動くタイミング」**でもあるのです。
このタイミングで情報漏洩が起きやすい理由は、大きく分けて2つあります。
1つは「うっかり」、もう1つは「意図的に」です。
① “うっかり”情報漏洩(過失)
「引き継ぎのつもりだった」「設定が残っていた」──
こうした善意や無意識、または従業員のミスにより、本人の意図していないところで情報を外に出してしまうケースです。
よくあるのはこんなパターン:
・アカウントの削除や権限の剥奪を“つい後回し”にしてしまう
・クラウドやデスクトップのフォルダが、私用アカウントと自動同期されていた
・「引き継ぎのため」として、業務データを個人PCやUSBにコピーしてしまう
本人に悪気はないことがほとんどですが、それでも漏洩は漏洩。
過失型の漏洩は、この退職の前後に集中しているという指摘もあるほどです。
② “意図的”な情報持ち出し(内部不正)
一方で、残念ながら一定数は**「故意の持ち出し」**=内部不正も起こっています。
こちらは、競合への転職や副業目的などを背景とした計画的な流出です。
たとえばこんなケース:
・退職後に顧客リストを使い、前職と同業の営業活動をスタート
・機密資料や業務ノウハウを個人フォルダにコピーし、自分の“資産”として再利用
・社内メールや提案書を私用PCに保存し、気づけば「自前の営業ツール」に
もちろん、すべての退職者がこうした行動をとるわけではありません。
ですが、**「数年後に競合からそっくりな提案が出てきた」**といった“遅れて気づく漏洩”も珍しくないのです。
このように、退職という日常的な出来事の裏には、
偶然のミスでも、意図的な行動でも、情報が外へ流れるリスクがあるという現実があります。
情報漏洩がもたらすリスク|思った以上に大きな「二次被害」
うっかりでも、意図的でも──
いったん情報が外へ漏れてしまえば、それで終わりではありません。
むしろ本当に怖いのは、「その先に起きる影響」です。
最近は、**情報漏洩が取引先や顧客、パートナー企業に波及していく“二次被害”**が増えています。
社内だけの話では収まらない。ここが今の情報管理のリアルな難しさです。
実際に、起きうる“二次被害”
-
顧客情報が流出し、損害賠償や取引中止に発展
-
委託先からの業務データが外部に漏れ、契約違反とされる
-
業界内での信頼が失墜し、採用や営業活動に支障が出る
-
“管理体制が甘い企業”として公的な監査対象になる
漏洩元がたとえ自社でなくても、関係企業から「貴社経由で漏れました」と言われれば、それは自社の責任になります。
このような連鎖型の被害は、特に中小企業にとっては大打撃です。
MEMO:二次被害は“外の世界”で拡張される
自社で完結していたミスが、取引先や顧客・委託業者などを巻き込み、
信用・契約・法的責任に発展することも珍しくありません。
だからこそ、まずは“自社から漏れない”体制を整えることが、最も現実的な予防策です。
「退職=情報が動く瞬間」であると同時に、
“その漏洩が社外で増幅される可能性がある”という前提も持っておくべき時代になっています。
▶ 身の回りの会社に迷惑をかけないためにも、まずは自社できちんと守れる仕組みを持つことが大切です。
こうした二次被害をはじめとしたセキュリティ被害については、以下の記事で詳しくまとめています。
気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
「気づいたら被害が甚大に…」と後悔しないために
ここまでご紹介してきたように、退職時の情報漏洩リスクは、
特別な事件ではなく、“日常のすきま”から誰でも起こしうるリアルな問題です。
しかも放置すれば、気づかぬうちに取引先や顧客にも波及して、
自社だけでなく、身の回りの会社を巻き込んだ深刻なトラブルへとつながる可能性もあります。
だからこそ──
「今うちは大丈夫かな?」
「うっかりしてないかな?」
そんな不安が少しでもよぎったら、今のうちから対策をしておきましょう!
とはいえ──
「何から手をつければいいのか、正直よくわからない…」
「ウチの場合はどうなんだろう?」
そんなふうに悩んでいる方も多いかもしれません。
そこで、まずは“ちょっと気になる”を話せる相談窓口をご用意しています。
現状の整理からでもOK。必要なら一緒に棚卸しもできますので、
ぜひお気軽にご利用ください!
この記事を書いた人
このライターの最新記事
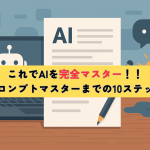 トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法
トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法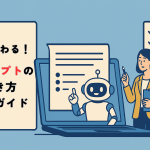 トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集
トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集 トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説
トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説 NEWS2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】
NEWS2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】


