詐欺の手口と対策をまるっと解説!だまされないために知っておくこと【2025年最新版】
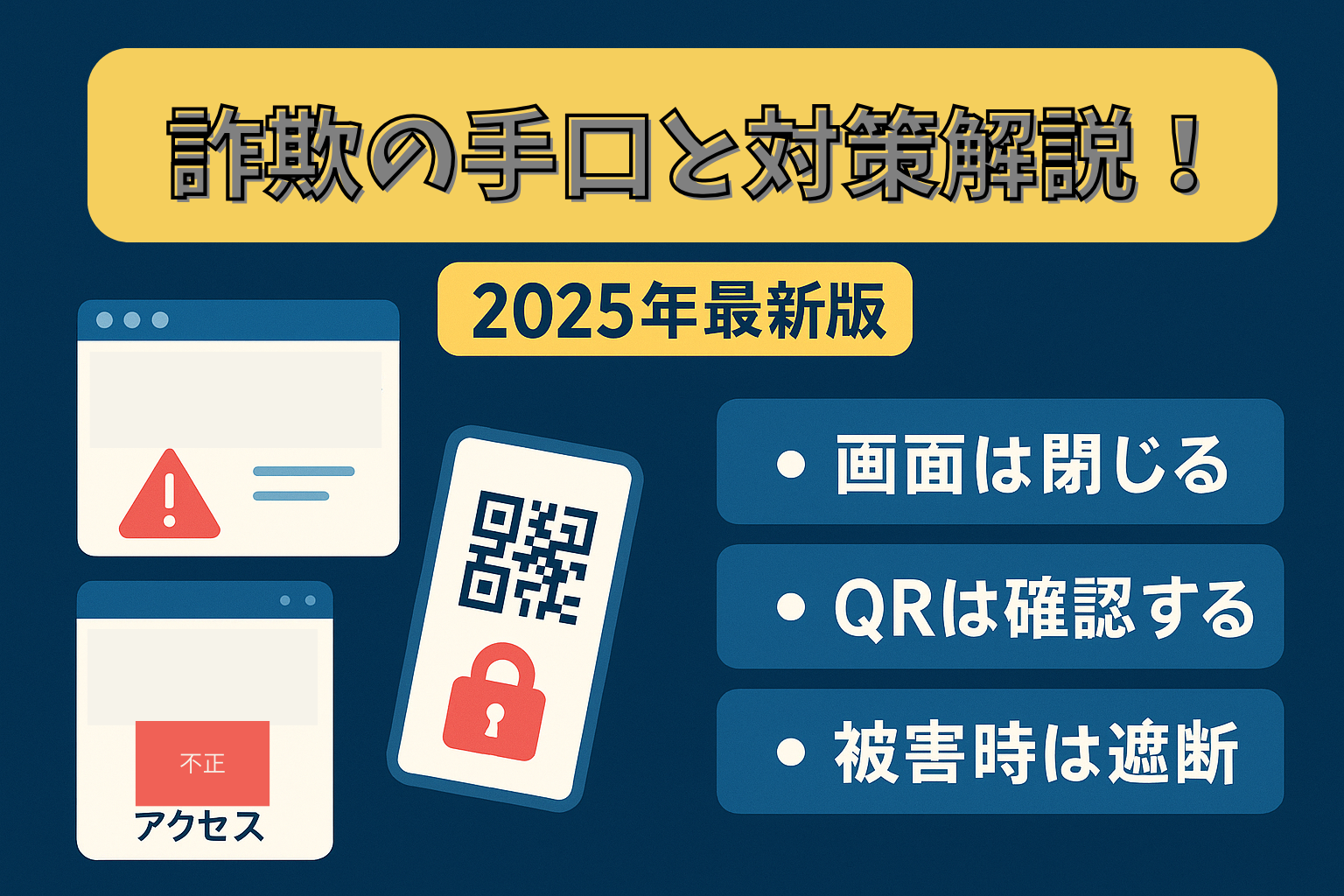
Menu
こんにちは、ixmedia編集部です!
最近、こんな画面やメッセージを見かけたことはありませんか?
-
「ウイルスに感染しました。今すぐお電話を!」
-
「このQRコードからログインしてください」
-
「あなたのアカウントに不正アクセスがありました」
一見それっぽく見えるメッセージ、
でもよく見ると――実はこれ、詐欺の可能性があります。
2025年の今も、サポート詐欺や、QRコードを使ったフィッシング(クイッシング)は、形を変えて身近に潜んでいます。
今回は、「どんな手口で来るのか」「どうやって防ぐのか」「やられてしまった時はどうするのか」まで、最新の傾向をもとにまとめました。
情報漏洩を防ぐためにも、今一度日常に潜むリスクを把握しておきましょう!
よくある詐欺①:サポート詐欺
画面に「ウイルス感染」などの警告を表示し、焦らせて電話やソフトのインストールを促す手口です。
見た目が本物っぽい作りで、「あれ?これ本当かも…」と信じてしまう人も少なくありません。
気づかないうちに“詐欺のサポートセンター”に誘導されてしまうことも…!
どんなふうに起きる?
-
広告などから不審なサイトにアクセス
-
画面いっぱいに「感染警告」や「不正アクセスの検出」を表示
-
偽のサポートセンターに電話をかけさせたり、ソフトをインストールさせたりする
実在する企業ロゴやそれっぽい警告音を組み合わせ、「これは本物かも…」と思わせてくるのが特徴です。
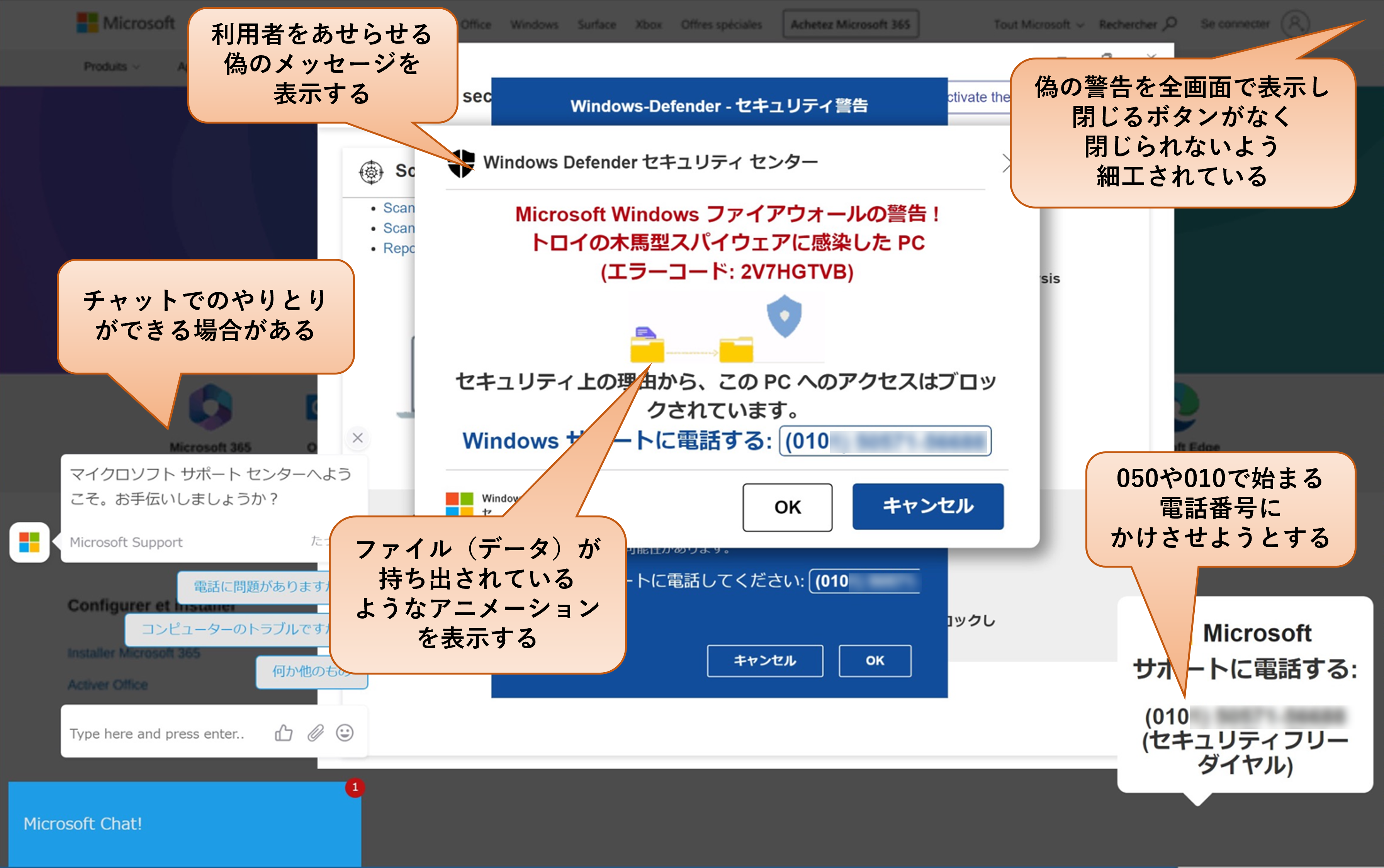
(引用:https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)
どうやって対策する?
-
ウイルス対策ソフトは“最初の盾”!しっかり入れておこう!
インストール&自動更新をONにしておけば、不審なファイル・URLを事前にブロックしてくれます。 -
“見た目がそれっぽい”に惑わされない
おかしな日本語、不自然な改行、ロゴの粗さなど、「どこかヘンじゃないか?」に気づく視点が大切です。 -
画面は信じず「閉じる」だけでOK!
電話番号が出ていても、その場でかけるのはNG。
閉じられないときは、Ctrl+Alt+Del → タスクマネージャー → ブラウザを「タスクの終了」で対処を。
それでも操作できなければ、再起動+公式サイトから確認しましょう。
▽さらに詳細を知りたい方はこちら
警察庁「サポート詐欺対策ページ」:https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/support-fraud.html
2025年最新のサポート詐欺
最近では、**AI音声を使った“偽サポート対応”**も報告されています。
電話をかけると、人間そっくりの声で案内が始まり、疑いなく指示に従ってしまう――そんな事例が増えてきているとのこと。
また、詐欺ページが本物の公式ドメインを模した1文字違いなど、ますます精巧になっています。
よくある詐欺②:QRフィッシング(クイッシング)
QRコードを読み取らせて、偽のログイン画面などに誘導し、個人情報を盗み取る詐欺です。
メール・ポスター・DMなど、見慣れた場所にひっそり仕込まれていることもあり、見抜くのが難しいのが特徴。
「いつものサービスっぽいから」と安心して進んでしまうと、「気づいたら落とし穴にはまってた」ということもあるので、要注意!
こんな場面に要注意!
-
メールに添付されたQRコード
-
ショートメッセージで届く「支払い確認」のリンク
-
店頭POPやポスターに貼られたQRコード
読み取ってみたら、見覚えのあるサービス画面そっくりのページに誘導されていた――
でも実はそこは偽物。入力した情報が盗まれてしまう…という仕掛けです。
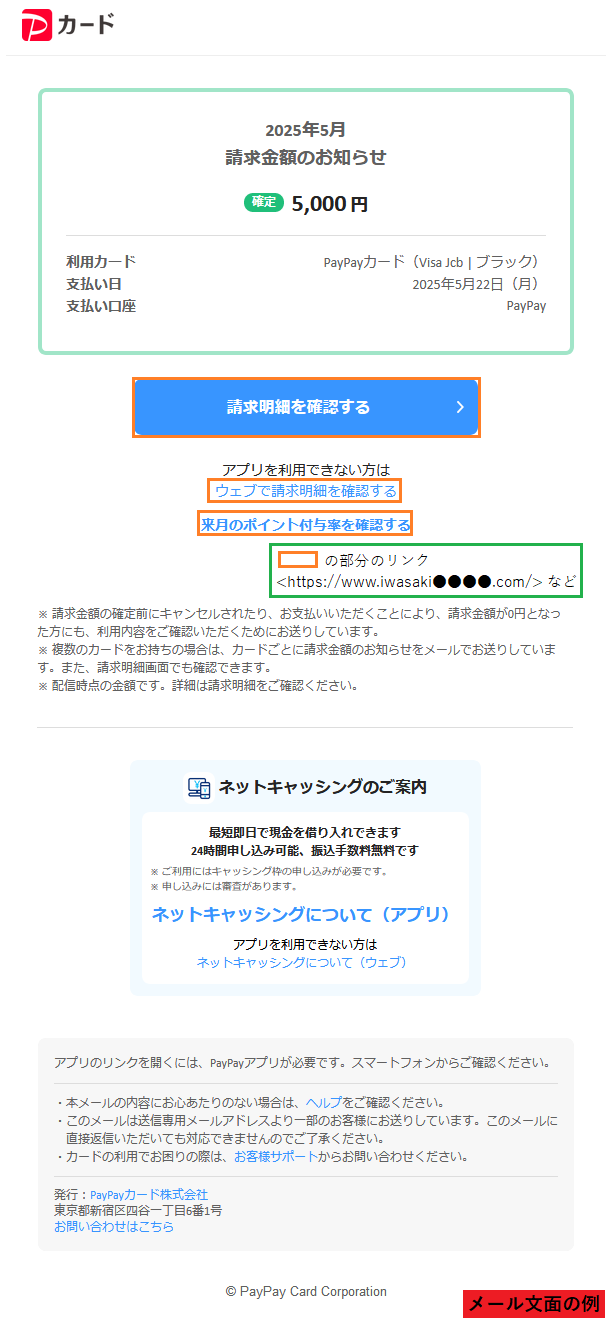
PayPayカードを騙るフィッシングメール例
(引用:https://www.antiphishing.jp/news/alert/paypay_20250521.html)
どうやって対策する?
-
“見知らぬQR”は読まないのが正解
差出人が不明だったり、「至急ログイン」など急がせる言葉があるQRコードには要注意。 -
読み取ってしまっても、アクセス前にURLをチェック
正しいドメインか?短縮URLじゃないか?1文字違いじゃないか?
――“一呼吸”置いて確認を徹底しましょう。 -
公式サイト・アプリから開き直す
よく使うサービスほど、“いつものアクセス経路”から再度ログインするほうが安全です。 -
社内共有も忘れずに!
手口の進化が早いため、社内掲示板やミニ研修などで最新の「だまし方」情報をシェアしておくと安心です。
▽さらに詳細を知りたい方はこちら
警察庁「フィッシング対策ページ」:https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html
2025年最新のフィッシング
特に今増えているのが、スマホ決済と連動した詐欺です。
Apple PayやGoogle Walletにカードを登録させ、そのまま不正使用する――というケースが広がっています。
また、「Smishing Triad」と呼ばれる国際的な詐欺グループの存在も注目されており、日本語を含む多言語での攻撃も巧妙化しています。
もし被害にあったら?
注意していたけど、もし被害にあってしまった場合…
そういう時はどうすればいいのか、もしっかりと把握しておきましょう。
1|まずは遮断すること
・ネット接続を一度切断(Wi-Fi・LAN)
・不審なソフトをアンインストール
・ウイルススキャンを実施
2|パスワードの切替
・被害が疑われるアカウントはすぐパスワード変更
・二段階認証(2FA)をオンに
3|関係機関へ連絡
・銀行やカード会社に不正利用の報告
・警察の「サイバー犯罪相談窓口」への通報
・企業内なら、情報システム部門へ即連絡
4|証拠はそのまま保存
・表示された画面やメール内容をスクリーンショット保存
・やりとりの記録・入力量・送金先などもメモしておくと、後の対応がスムーズに!
まとめ|「従わない・踏み込まない」それだけで守れる!
-
サポート詐欺は「焦って電話しない」「画面は閉じる」でOK
-
クイッシングは「知らないQRを読まない」「公式からアクセスし直す」でOK
-
もしものときは、落ち着いて遮断・切替・報告・保存を徹底!
セキュリティは“全部やる”より“ポイントを押さえる”が大事。
無理なく、でも着実に、身の回りの安全を守っていきましょう。
番外編|退職・異動の時期の情報漏洩に注意!
「うちは詐欺被害はないな」と感じている方も、別のルートからの情報漏洩にも注意しましょう。
特に、最近の報告では、情報漏洩の原因として「退職者による情報漏洩」が一番多くを占めています。
**“人が動く時=情報が動く時”**という落とし穴を忘れずに。
-
クラウドの共有リンクがそのままになっていた
-
自動転送メールが止まっていなかった
-
私用クラウドに業務データが同期されていた
退職・異動・組織改編などのタイミングは、うっかりミスによる漏洩が起きやすい時期です。
以下の記事で、具体例と対策をまとめています。あわせてご確認ください!
この記事を書いた人
このライターの最新記事
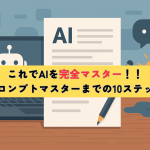 トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法
トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法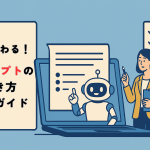 トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集
トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集 トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説
トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説 トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】
トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】


