誰でもわかる!AIを活用するメリット・デメリットを知っておこう【2025年版】
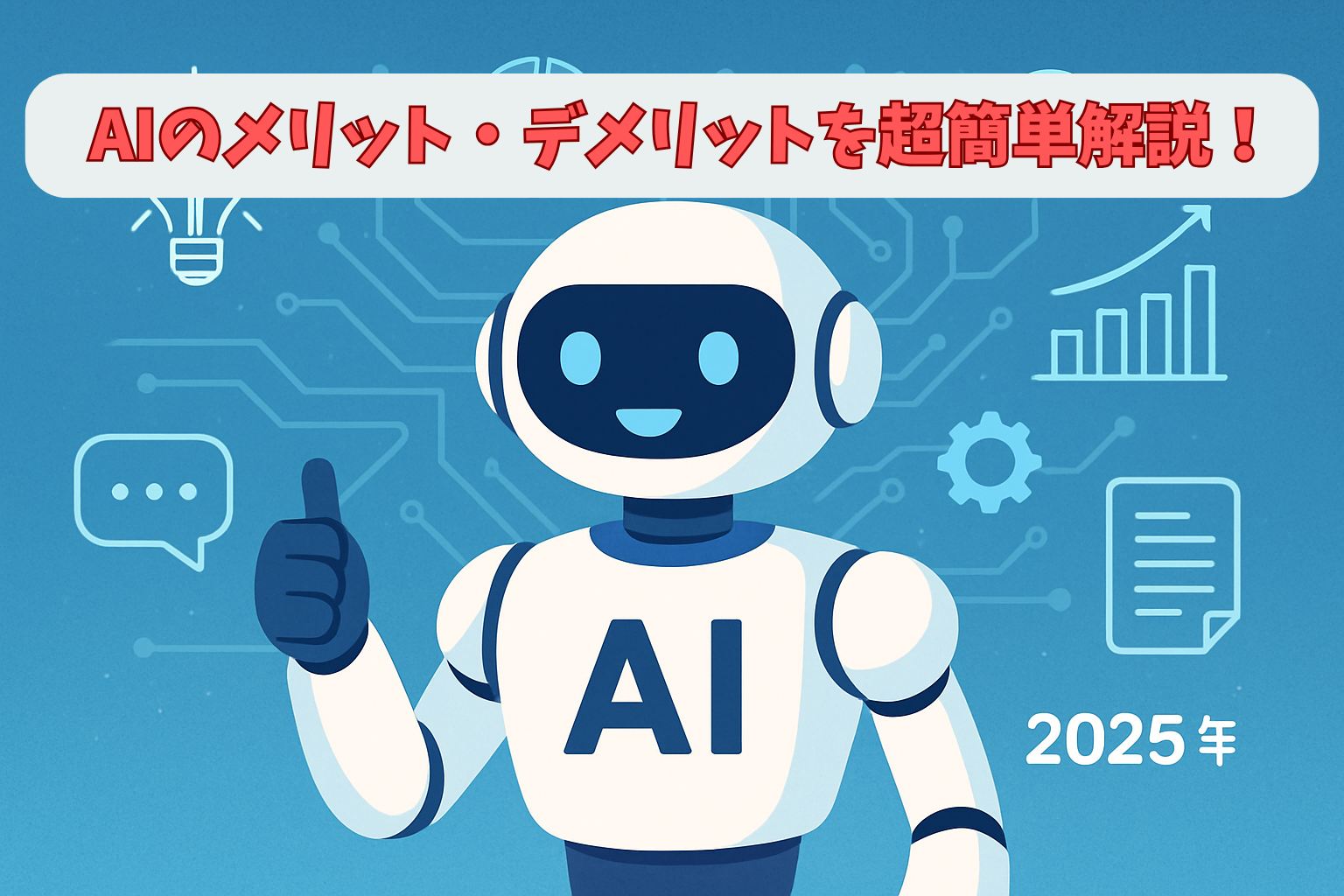
Menu
こんにちは、ixmedia編集部です。
「最近、AIってよく耳にするけど、正直まだ触ったことがない」
「便利そうだけど、何から始めればいいのか分からない」
そんな声をよく聞きます。
AIは難しい専門家だけのものではなく、今や日常の仕事や生活をサポートしてくれる存在になっています。
そこで、本記事では、“AIを初めて使う方”に向けて、基本の考え方や活用のヒントをわかりやすくまとめましてみました。
AIは使いこなせれば、日々の業務の大きな武器となるので、ポイントを抑えてしっかりと活用していきましょう!
AIの基本:相棒みたいなツール
生成AIは、よく「もう一人の自分」「自分の相棒」といったような表現をされます。
文章や画像を作ったり、長文を要約したり、外国語を翻訳したり、アイデアを出したり――まるで万能アシスタントのように幅広くサポートしてくれます。
AIというと「魔法のように何でもやってくれるもの」と思われがちですが、
実際には“速く形にしてくれる相棒”というイメージがぴったりです。
-
長い文章を短くまとめる
-
難しい言葉をやさしく言い換える
-
アイデアを出すときの壁打ち相手になる
例えば「報告書を3つのポイントにまとめて」とお願いすれば、要点を整理した短い文章が数秒で返ってきます。
まるで「苦手な資料作りをサッと助けてくれる同僚」のような存在です。
仕事でどう役立つ?具体的なシーンも解説!
AIの魅力は多岐に渡りますが、やはり多くの人が感じているのは「業務効率化」や「斬新なアイデア」。
実際、総務省の調査でも、「生成AI活用による効果・影響」の調査を実施した結果、
1位「業務効率化や人手不足解消につながる」
2位「ビジネスの拡大や新たな顧客獲得につながる」
3位「斬新なアイデア/新たなイノベーションが生まれる」
となっています。
(参照:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html)
では、実際にどういったシーンでAIを活用できるのでしょうか。
-
議事録作成
会議の内容を「要点3つ+ToDo+担当者+期限」で整理。
たとえば「決めたこと」と「次やること」が分かれて出力されるので、あとから「結局誰が動くんだっけ?」と迷うことが減ります。
実際、手書きやExcelでまとめていた頃に比べて、議事録作成の時間が半分以下になるケースも。 -
資料のわかりやすさアップ
提案書や稟議書に専門用語が並ぶと、現場の人や経営層には伝わりにくいことがあります。
そこでAIに「難しい単語に一文だけ注釈をつけて」と指示すると、読み手に優しい資料に。
たとえば「SaaS(インターネット経由で利用するソフトウェアの仕組み)」のように補足されるイメージです。 -
アイデア出し
「このサービスを紹介するキャッチコピーを3案」と依頼すれば、切り口の違う表現が並びます。
営業チームならA案を経営層向け、B案を現場向け、といった形で使い分けも可能。
ブレストのスタートラインを早く切れるのが強みです。 -
問い合わせ対応
社内の情シス(情報システム部門)や総務には、同じような質問が毎日のように届きます。
AIに「よくある質問をテンプレ化して」と頼めば、雛形を自動で整えてくれます。
社員が自分で解決できる比率が上がり、担当者の負担も軽くなります。
こうした“小さな一歩”だけでも「会議のあとがラクになった」「資料の手戻りが減った」と実感できることが多いのがAIです。
生活の中でも役立つAI
ちなみに、生成AIは、工夫次第でプライベートでも役立てることができます。
例えば…
-
旅行プラン
「週末に子どもと行ける2泊3日のモデルコースを作って」と伝えると、移動時間や子ども向けスポットも考慮した旅程を提案してくれます。
観光名所と食事場所がセットで出てくるので、「昼ごはんどうする?」で慌てなくて済みます。 -
料理や健康管理
食事の写真を見せて「たんぱく質は何グラム?」と聞くと、栄養バランスのアドバイスも。
献立提案も得意で、「余っている野菜で作れる夕食3案」なんてリクエストも可能。
健康管理アプリ代わりとしても使えます。 -
ちょっとした相談
「忙しすぎて、何から手をつければいいか分からない」と入力すると、「今日中に終わらせたいこと」「来週でも大丈夫なこと」に整理してくれることも。
頭の中のモヤモヤが見える化されるだけで、気持ちがスッと軽くなります。
「難しい仕組みを理解する」よりも、「困ったときに聞いてみよう」と思えるかどうかが大切です。
気をつけたいポイント
AIはとても便利ですが、「安心して使うためのコツ」もあります。
実際、AIを活用するうえで、一番不安な点としてよく取り上げられるのが「情報漏洩」
誰でもクラウドで使える分、社内の機密情報や個人情報は、かなり相談しにくいのが現状です。
ここでは、初めてAIを取り入れる方でも意識しておきたい注意点をまとめました。
- 個人情報は入力しない
「パスワード」「顧客リスト」「契約書の全文」など、社外秘のデータは入力しないこと。
これはどのAIサービスにも共通する基本ルールです。
国の指針でも、こうした情報管理の徹底が明記されています。
(参照:経済産業省|AI事業者ガイドライン
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20250328_3.pdf)
-
情報の正確さ
AIはときどき誤った情報を提示することがあります。
特に数字や法律、医療関係は「必ず一次情報を確認する」のが基本です。
たとえば「補助金の申請期限」などを調べるときは、必ず公式サイトで裏を取る必要があります。 -
使いすぎ注意
便利だからと全部AIに任せると、「考える力」が育たなくなります。
たとえば文章の骨組みをAIに作らせても、最後の言い回しや判断は人が手を入れる。
このバランスを意識することで、業務の質を守りながら効率化できます。
経済産業省の資料でも「便益とリスクを両にらみでの活用」が推奨されています。
つまり“うまく取り入れて、自分の判断力も残す”ことが大切なのです。
まとめ:まずは簡単なところから始めてみよう
AIは、特別な知識やスキルがなくても気軽に試せるツールです。
-
「この文章をやさしく書き直して」
-
「今日の会議を3行でまとめて」
-
「忙しいときのタスク整理を手伝って」
そんな“ひとこと”からでも十分に始められます。
最初は「こんなことで使っていいのかな」と迷うかもしれません。
ですが、一度体験すると「あれも頼めるかも」と新しい使い方が見えてきます。
AIは“知識を教えてくれる先生”ではなく、“一緒に考えてくれる相棒”。
あなたの毎日の仕事や生活を、ちょっとラクに、ちょっと楽しくしてくれる存在です。
使い方の注意点を抑えながら、AIを活用していきましょう!
知っておけば「ちょっと差がつく」お得な情報発信中!
当メディア「ixmedia」では、知ってるだけで日頃の生活が「ちょっと差がつく」お得な情報を発信中!
今回のような「AI」に関する話題をはじめ、
ITやDX化、セキュリティ対策に関するトレンドな情報を日々発信しております!
今回の記事が「役に立った!」という方は、ぜひ他の記事も読んでみてください。
「ixmedia」他の記事はこちらから
この記事を書いた人
このライターの最新記事
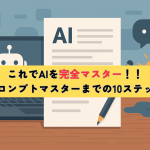 トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法
トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法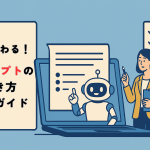 トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集
トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集 トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説
トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説 トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】
トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】


