AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集
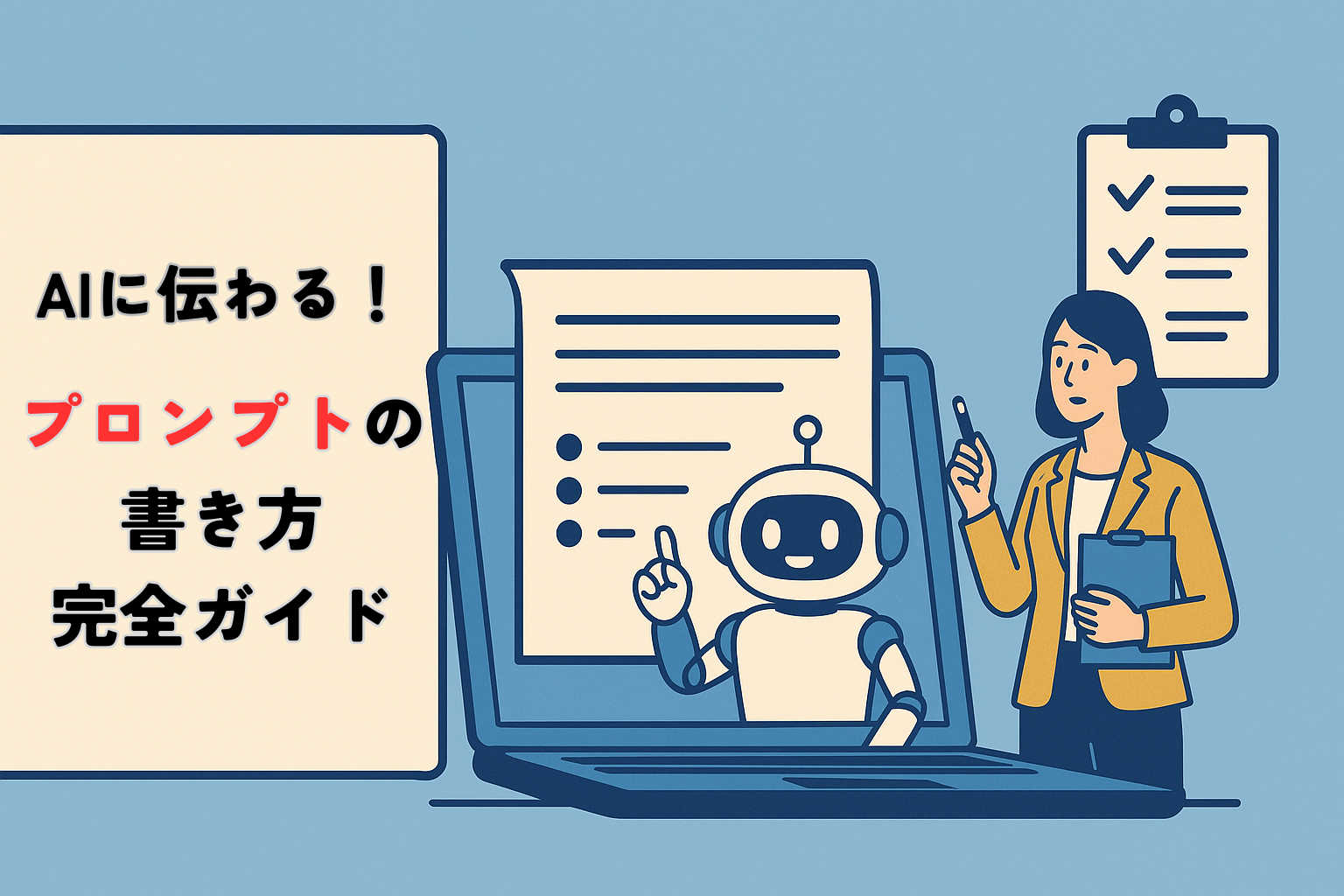
こんにちは、ixmedia編集部です。
「AIに頼んでみたけど、なんか思った通りの結果が出ない…」
「もっと具体的に書いてって言われても、どう伝えればいいの?」
AIを使い始めた方なら、きっと一度は感じたことがある悩みではないでしょうか。
せっかく便利なツールがあるのに、うまく使えないともどかしいですよね。
実は、AIが思うように動かない原因の多くは「伝え方」にあります。
AIは確かに賢いツールですが、私たちの頭の中を読み取ってくれるわけではありません。
つまり、どれだけ明確に「何をしてほしいか」を伝えられるかが、成果を左右するのです。
本記事では、AIを正しく動かすための「プロンプト(指示文)」の書き方を、実務で使える具体例とともに解説します。
読み終わる頃には、「AIがもっと身近に感じられる」「明日から試してみよう」と思っていただけるかと思います!
ちょっと差がつくコソ勉メディア「ixmedia」記事公開中!
ixmediaでは、知ってるだけで日頃の生活が「ちょっと差がつく」お得な情報を紹介しています。
AI活用をはじめとして、DX化、セキュリティなどITにまつわるトレンドな情報を日々発信しております!
・【2025年最新版】ChatGPTがここまで進化!最新機能&使い方ガイド 【画像付き】
AIは魔法ではなく、自分を映す鏡
AIの本当の役割を理解とは?
まず、知っておくべきことは、
AIの力は「質問の仕方」で大きく変わるということです。
AIは、「魔法のように何でも叶えてくれる存在」ではありません。
実際には、AIは「あなたの意図を映し出す鏡」のような存在です。
例えば、鏡に向かって「きれいに映して」と言っても、鏡は何も変わりません。
大切なのは、鏡の前に立つ私たち自身の姿勢や表情です。
AIも同じで、私たちが明確で具体的な指示を出せば出すほど、期待に近い結果を返してくれます。
人を拡張する存在としてのAI
AIは人を置き換える存在ではなく、私たちの能力を拡張してくれるパートナーです。
つまり、AIに正しく指示を出せるということは、自分の考えを整理する力が身についているということでもあります。
「何を作りたいのか」「どんな形で出力してほしいのか」「誰に向けた内容なのか」
こうした要素を言語化できるようになると、AI活用だけでなく、日常の業務でも「伝える力」が向上します。
欲しい答えを返してもらうためのプロンプト作成 3ステップ
良いプロンプトを作るコツは、実はとてもシンプルです。
以下の3ステップを意識するだけで、AIの回答精度が格段に向上します。
①目的と状況を明確に伝える
まずは「何のために」「誰に向けて」作るのか、そして「どんな状況で」使うのかを明確にしましょう。
AIは言葉そのものよりも、“背景”を理解することで正確に応えてくれます。
例えば、あなたの会社の業種、抱えている課題、前提条件を一言添えるだけで、答えの質は大きく変わります。
悪い例:
「営業資料を作って」
良い例:
「建設業の中小企業向けに、初回商談で使う営業資料を作って。目的はコスト削減提案に興味を持ってもらうこと」
このように、目的と状況をセットで伝えることで、AIは「どんな視点・トーンで書くべきか」を正確に判断できるようになります。
要するに、“AIに考える材料を渡す”ことが大切なのです。
②形式を具体的に指定する
次に、「どんな形で出力してほしいか」を具体的に伝えます。
悪い例:
「わかりやすくまとめて」
良い例:
「3つのポイントに分けて、それぞれ2行程度で説明。見出しは太字で表示」
文字数、構成、見た目まで指定することで、後から手直しする時間を大幅に短縮できます。
③結果の確認・修正を繰り返す
AIが一発で出した答えをそのまま使うのではなく、
必ず内容を確認し、必要に応じて修正指示を出しましょう。
修正例:
「もう少し親しみやすいトーンに変更して」
「専門用語に簡単な説明を括弧内で追加して」
この「やり取り」を重ねることで、より理想に近い結果を得られます。
実務シーン別:よくある失敗と改善例
AIに「やってほしいこと」は伝えているのに、なぜかピントがずれて返ってくる――。
その多くは、“目的だけ”を伝えて、“状況”を伝えていないことが原因です。
AIは文脈を前提に判断するため、
「誰に」「どんな場面で」「何のために」使うのかを一言添えるだけで、出力の精度が大きく変わります。
ここでは、実際の業務シーンでよくある例を使って、
「失敗しがちなプロンプト」と「状況を含めた改善例」を比較してみましょう。
営業資料の作成
■失敗例❌
「弊社サービスの提案書を作って」
■改善例✅
「製造業の中小企業向けに、弊社のクラウド会計サービスを提案する資料を作成してほしい。
目的はコスト削減効果を具体的に伝えること。
既存の会計ソフトからの移行を検討している層を想定。A4で3ページ程度」
💡ポイント:
「誰向け」「どんな背景」「どんな目的」が入るだけで、AIが“話の筋”を理解しやすくなります。
特に、相手の業種や課題を明示すると、AIはより現実的な表現を選ぶ傾向があります。
社長メッセージの作成
■失敗例❌
「年始の挨拶文を書いて」
■改善例✅
「従業員50名の地方製造業として、年始の社内向け挨拶文を作成してほしい。
昨年の売上20%増を報告し、今年の新工場稼働への期待を伝えたい。
前向きで温かいトーンで、400文字程度」
💡ポイント:
“どんな組織で、どんな1年だったか”を入れると、AIが使う語彙やトーンがぐっと人間的になります。
議事録の要点整理
■失敗例❌
「会議の内容をまとめて」
■改善例✅
「営業・マーケ合同会議の内容を『決定事項』『課題・懸念点』『次回までのアクション(担当者・期限)』の3項目に分けて整理して。
5人会議で30分程度の内容。各項目は箇条書きで」
💡ポイント:
AIにとって“会議の規模”や“関係部署”は重要な前提情報です。
具体的な条件を入れるだけで、「誰の視点でまとめるか」を自動的に調整してくれます。
メールの適切なトーン
■失敗例❌
「お客様への謝罪メールを作って」
■改善例✅
「**納期遅延(部品供給の遅れが原因)**についてお客様へ謝罪メールを作ってほしい。
長年取引のある相手に誠実さを伝えたい。
事実説明→謝罪→原因→再発防止→締め、の順で構成。200文字程度」
💡ポイント:
“どんな関係性の相手か”や“トラブルの性質”を入れることで、AIの言葉選びが適切になります。
即効使えるプロンプト|万能フレーズ集
どんな職種でも使える、コピペで活用できるフレーズをご紹介します。
以下のような「目的+状況+形式」を意識するだけで、AIの回答は格段に実務的になります。
基本フレーズ:誰でも使える汎用プロンプト
状況を添える
-
「建設業の中小企業として」「飲食業の現場向けに」「リモートワーク中のチームに伝える内容で」
-
「繁忙期に向けた準備として」「社内共有用として」「初回提案用として」
わかりやすさ重視
-
「中学生でも理解できるように」
-
「専門用語を使わずに」
-
「具体例を交えて」
構成・形式指定
-
「3つのポイントに分けて」
-
「結論を最初に述べて」
-
「箇条書きで」
-
「表形式で整理して」
トーン調整
-
「親しみやすいトーンで」
-
「ビジネス文書として適切な敬語で」
-
「前向きで明るい印象になるように」
文字数・分量指定
-
「200文字程度で」
-
「A4用紙1枚に収まる分量で」
-
「1分で読める長さで」
職種別の実用例
営業・企画職向け
「製造業の顧客向けに、競合他社との差別化ポイントを3つ挙げて。それぞれ顧客メリットの観点から100文字程度で説明」
総務・人事向け
「新入社員向け研修案内メールを作成。社内文化を伝えたいが、堅すぎないトーンで。日時・場所・持ち物を明記」
広報・マーケティング向け
「飲食業界向けの新サービス発表リリース。革新性と業界インパクトを強調しつつ、30文字以内の見出し案を5つ提案」
まとめ:AIはあなたの参謀役
プロンプト力が磨かれると広がる可能性
良いプロンプトを書けるようになると、AIとの「会話」がスムーズになります。
まるで優秀なアシスタントと息の合った連携ができるように、短時間で質の高い成果物を作れるようになるのです。
また、プロンプトを考える過程で「自分が本当に求めているもの」が明確になります。
これは、AI活用に限らず、部下への指示出しや、社外とのやり取りでも活かされる力です。
今日から始める一歩の大切さ
「完璧なプロンプトを書かなければ」と構える必要はありません。
まずは今回ご紹介した3ステップを意識して、簡単な作業から始めてみてください。
例えば:
- 「今日の会議を3行でまとめて」
- 「このメールをもう少し丁寧なトーンに変更して」
- 「来週のプレゼン資料の構成案を5つ考えて」
こんな「ひとこと」からでも十分です。
AIは命令で動かす存在ではなく、会話を重ねながら一緒に成果を作り上げる相棒です。
使いこなす人と振り回される人の差は、まさに「伝え方」にあります。
ぜひ今日から、AIとの新しい付き合い方を始めてみてください。
きっと「もっと早く知りたかった」と思える発見があるはずです。
ちょっと差がつくコソ勉メディア「ixmedia」記事公開中!
ixmediaでは、知ってるだけで日頃の生活が「ちょっと差がつく」お得な情報を紹介しています。
AI活用をはじめとして、DX化、セキュリティなどITにまつわるトレンドな情報を日々発信しております!
・【2025年最新版】ChatGPTがここまで進化!最新機能&使い方ガイド 【画像付き】
・AIを活用するメリット・デメリットを知っておこう【2025年版】
・AIって何を使えばいい?|誰でもわかる「AIの種類」超入門【2025年最新版】
この記事を書いた人
このライターの最新記事
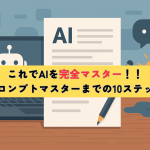 トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法
トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法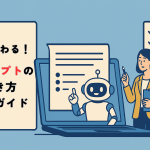 トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集
トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集 トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説
トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説 トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】
トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】


